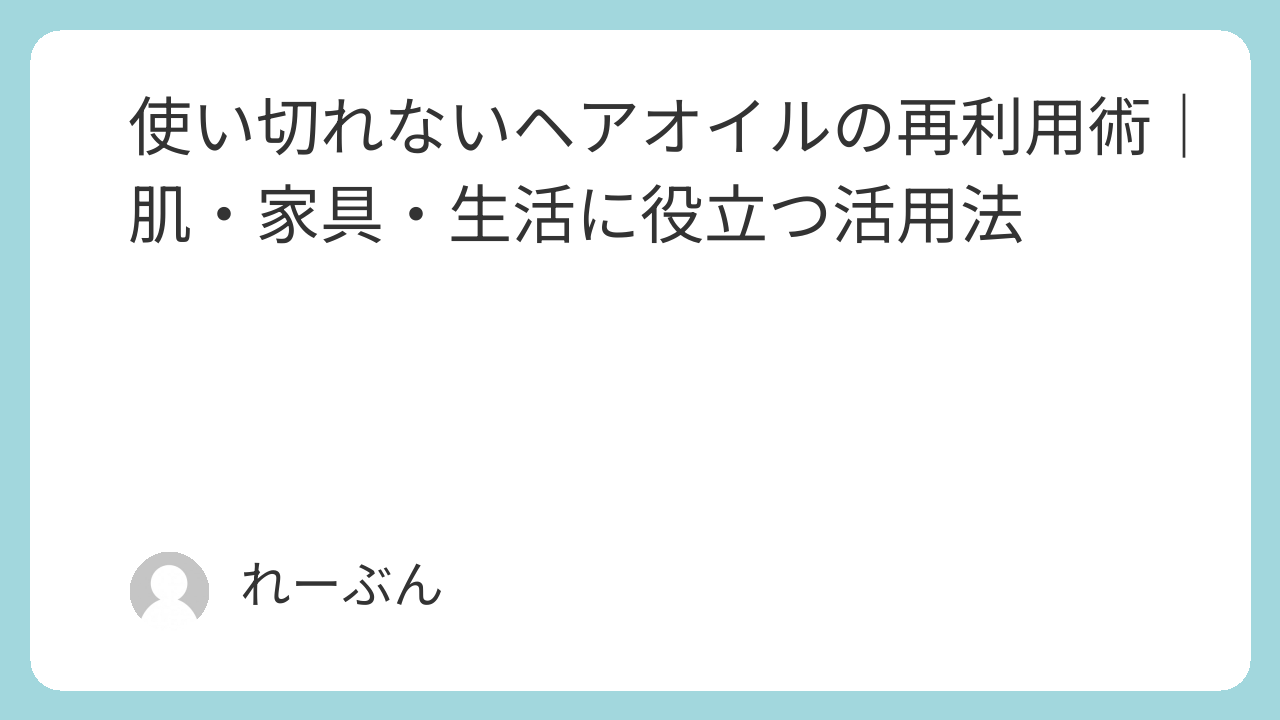ヘアケアのために購入したヘアオイル、気がつけば使い切れずに残っていませんか?
「香りが合わなくなった」「使い道が限られている」「肌に合わなかった」など、理由はさまざま。
でもそのまま処分してしまうのは、なんだかもったいないですよね。
実は、余ったヘアオイルには髪以外にもたくさんの活用方法があるんです。
この記事では、思わず試したくなる活用術をご紹介します。
おうち時間を豊かにするヒントとして、ぜひ最後までご覧ください。
どうしてヘアオイルは余りやすいの?

ヘアオイルは髪の毛のケアに便利なアイテムですが、「使い切れなかった…」という経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
ここでは、ヘアオイルが余ってしまう理由と、捨てる前にぜひ知っておきたいメリットについてご紹介します。
最後まで使い切れない理由あるある
こんな理由で、気がつけば洗面台の奥や収納棚の隅に置きっぱなし、ということもありますよね。
「いつか使おう」と思っていたのに、気づいたら賞味期限(使用期限)が迫っていた、という経験をされた方もいるかもしれません。
成分や香りの好みが変わって使わなくなるケース
ヘアオイルにはさまざまな成分や香りがあります。
オイルによっては、しっとりタイプやさらさらタイプ、重ための質感や軽い仕上がりなど種類が豊富です。
購入時には「いい香り!」と思っていたものも、気分の変化、季節の変化によって「ちょっと強すぎるかも…」と感じることも。
また、体調の変化によって香りに敏感になる時期もあるため、急に使わなくなることもあります。
「もう合わないな」と感じたら、無理に使わず別の使い道を探すのがおすすめです。
捨てる前に知っておきたい!再利用のメリット
余ったオイルを上手に暮らしに取り入れることで、「捨てるのはもったいない…」という罪悪感も軽くなります。
例えば、革小物や家具のお手入れに使えばピカピカに。
また、ほんの少し使うだけでもしっかり効果を感じられるので、「節約しながら贅沢気分」を味わえるのが嬉しいポイントです。
さらに、無駄なく使い切ることで環境にもやさしく、ちょっとしたエコ習慣にもつながります。
「何かに使えるかも」と思って手元に置いているヘアオイル。
ぜひ新しい使い道を見つけて、最後まで気持ちよく使い切ってみましょう。
髪にやさしい再利用方法
髪全体に使うには重たく感じても、毛先だけに少量なじませればまとまりやすくなります。
パサつきや広がりが気になるときに試してみてくださいね。
翌朝の寝ぐせ防止にも役立ちます。
暮らしの中でも使える!生活の便利アイデア

ヘアオイルは美容だけでなく、暮らしのちょっとした場面でも役立つアイテムです。
家にあるものでちょっと工夫するだけで、意外と便利に使えるんですよ。
革製バッグ・財布の艶出しと保湿に
乾燥してカサカサになった革小物に少しなじませると、ツヤがよみがえります。
特に冬場や長く使っているお気に入りのバッグには、定期的なお手入れが欠かせません。
オイルは乾いた布にごく少量とり、くるくると優しく円を描くように塗り広げるのがポイントです。
革製品の種類によっては、目立たない場所で試してから使うと安心です。
やさしく布で拭き取るように使ってくださいね。
ツヤが出るだけでなく、ひび割れの防止や柔らかさの維持にも役立ちます。
木製家具の艶出しや乾燥防止に使う
オイルを布に取り、木のテーブルや椅子に優しく塗ると、自然なツヤと保湿効果があります。
特に乾燥して白っぽくなってしまった箇所には効果的で、木目が美しくよみがえります。
使う前に軽くホコリを取っておくと、よりきれいに仕上がります。
定期的にお手入れすれば、家具の寿命をのばすことにもつながります。
無垢材のケアにおすすめです。
金具やファスナーの滑りを良くする
かたいファスナーや、動きが悪い引き出しにも少量のオイルを。
綿棒やティッシュを使って、少しずつ塗ってみてください。
金属部分のさび予防にもなり、長く快適に使えます。
子どもの通園バッグや旅行用のスーツケースなど、頻繁に開け閉めするものにも活用できます。
ドアや家具のきしみ音を軽減する
「ギィ…」という音が気になるドアのヒンジ部分にオイルを少し垂らすと、動きがスムーズになります。
一度塗るだけでも驚くほど静かになりますが、しばらく時間をおいてからもう一度なじませるとより効果的です。
布やスポンジに染み込ませて塗ると手も汚れにくく、安全に作業できます。
靴磨きやレザーシューズのお手入れにも
黒ずみや乾燥が気になるレザー靴に、やわらかい布でオイルを塗ると、つややかに整います。
とくに雨に濡れてしまった後や、季節の変わり目にはこまめなお手入れが大切です。
靴の表面だけでなく、かかとやつま先などのすれやすい部分にもやさしくなじませると◎。
仕上げに乾いた布で拭き取ると、さらになめらかな仕上がりになります。
ヘアオイルの種類によって使い方は変わる?

オイルといっても種類はさまざま。
どのようなオイルかによって、再利用先の向き不向きもあります。
天然オイル(アルガン・ホホバなど)の再利用に向いている用途
植物性のオイルは、保湿力も高いため、ハンドケアやマッサージにも使えます。
さらに、家具のお手入れにもぴったりで、木製のテーブルやイスにオイルをなじませると、乾燥によるひび割れを防ぎ、自然なツヤを与えてくれます。
リップクリーム代わりに少量を唇の周りに使う方法や、ひと吹き香水代わりに香りのついていない天然オイルを首元に塗って使う方法もあります。
シリコン系オイルの活かし方と注意点
ツヤ出し効果は高いです。
ファスナーや家具の滑り改善に特化して使うと安心です。
また、バッグのファスナー部分や玄関ドアの蝶番(ちょうつがい)などにも少量塗ると、動きがなめらかになります。
つやを出したい合皮バッグや靴にも向いており、布で薄く拭き取るように使うのがおすすめです。
ただし、素材によっては変色やべたつきが起こる場合があるため、事前に目立たない場所で試してから使いましょう。
香りつきオイルのリラックス活用法
お気に入りの香りのオイルは、寝る前に手首や首元につけて香りを楽しむ使い方も素敵です。
香りがふんわり広がるので、眠る前の習慣に取り入れている方もいます。
アロマ代わりに使うことで気分転換にもなります。
たとえば、ティッシュやハンカチに一滴垂らしてポーチに忍ばせたり、デスクに置いておくと、ちょっとしたリフレッシュタイムに役立ちます。
お気に入りの本に少量しみ込ませて、香りのブックマークにしている人もいます。
香りを楽しむことで最後まで無駄なく使い切ることができます。
実際に試してみた!再利用してよかった体験談

「捨てるのはもったいない」と感じて使ってみたら、意外な便利さに驚いたという声もたくさんあります。
家具や雑貨に使ってみた使用感と気づき
古くなった机に塗ってみたらツヤが出て、見た目がぐっとよくなりました。
乾燥していた木目がしっとりとよみがえり、お部屋全体の雰囲気まで明るくなったような気がします。
しかもほんの少しの量で十分なので経済的です。
お手入れ後の家具に触れると、手触りもやわらかくて気持ちよく、ますます愛着がわいてきました。
お気に入りの木製トレーや、飾り棚の小物にも使ってみたところ、見た目の質感がグンとアップしましたよ。
失敗から学んだ「やりすぎ注意」のポイント
使いすぎるとベタベタになったり、香りが強すぎて気になることも。
家具の場合は塗りすぎるとシミになったり、滑りやすくなることもあったので要注意です。
適量を守って少しずつ試すのが安心です。
特に香りが強いタイプは、部屋の中でも思った以上に残ることがあるため、換気や場所選びも意識すると◎。
最初は目立たない場所でテストしてから、本格的に使うのがおすすめです。
よくある質問Q&A|初心者さんも安心
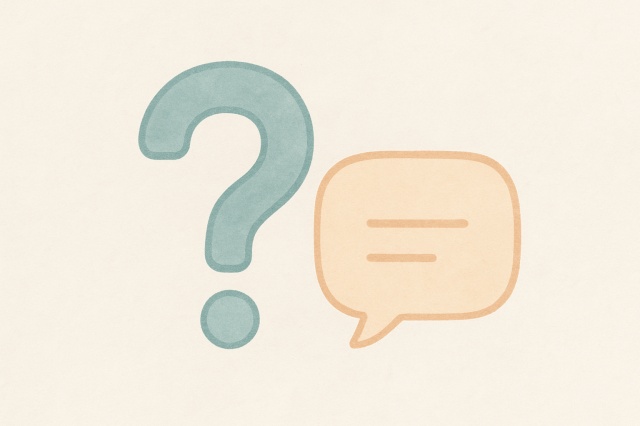
開封後どのくらいで使い切るのが理想?
目安は1年以内。
保管状態にもよりますが、香りや色に変化があれば使用を避けましょう。
香りが強すぎる場合のおすすめ再利用法
布製ポーチやハンカチに少量つけて香りを楽しむ工夫ができます。
プレゼントとしておすそ分けする方法はある?
きれいな容器に詰め替えれば、ちょっとした贈り物にもなります。
ただし、使用期限や保存方法なども一緒に伝えると安心ですね。
意外と知られていない!こんな活用方法も
ハンドメイド作品やアクセサリーのコーティングに
天然石やレザーを使った作品に、薄く塗ることで光沢が出ることもあります。
特にレザー素材のブレスレットや、くすみが気になるパーツに少量塗ると、見た目の高級感が増して長く愛用できます。
また、ワイヤーや金属製のアクセサリー部分に薄く塗ると、空気との接触を軽減してサビを防ぐ効果も期待できます。
キーホルダーやスマホケースの一部など、身近な小物にも応用可能です。
塗りすぎるとベタついてしまうため、綿棒や小さなブラシを使って丁寧に塗り広げると仕上がりがきれいです。
自己流で少しずつ試してみてください。
キッチンや洗面所まわりの収納にも応用できる?
引き出しの滑りが悪いときや、金具の動きをスムーズにしたいときに活躍します。
例えば、洗面台下の収納引き出しや、キッチンの調味料ラックなどで動きが悪くなった部分に、少量のオイルを塗布することでスムーズに動くようになります。
ただし、食品や水回りへの使用は避けましょう。
また、使ったあとはしっかりと拭き取り、周囲に残らないようにすると安心です。
まとめ|余ったヘアオイルで毎日がもっと快適に
余ってしまったヘアオイルも、ちょっとした工夫で暮らしの味方になります。
上手に取り入れて、最後まで気持ちよく使い切ってみましょう。
やさしい再利用で、自分にも環境にもやさしい毎日を過ごしてくださいね。