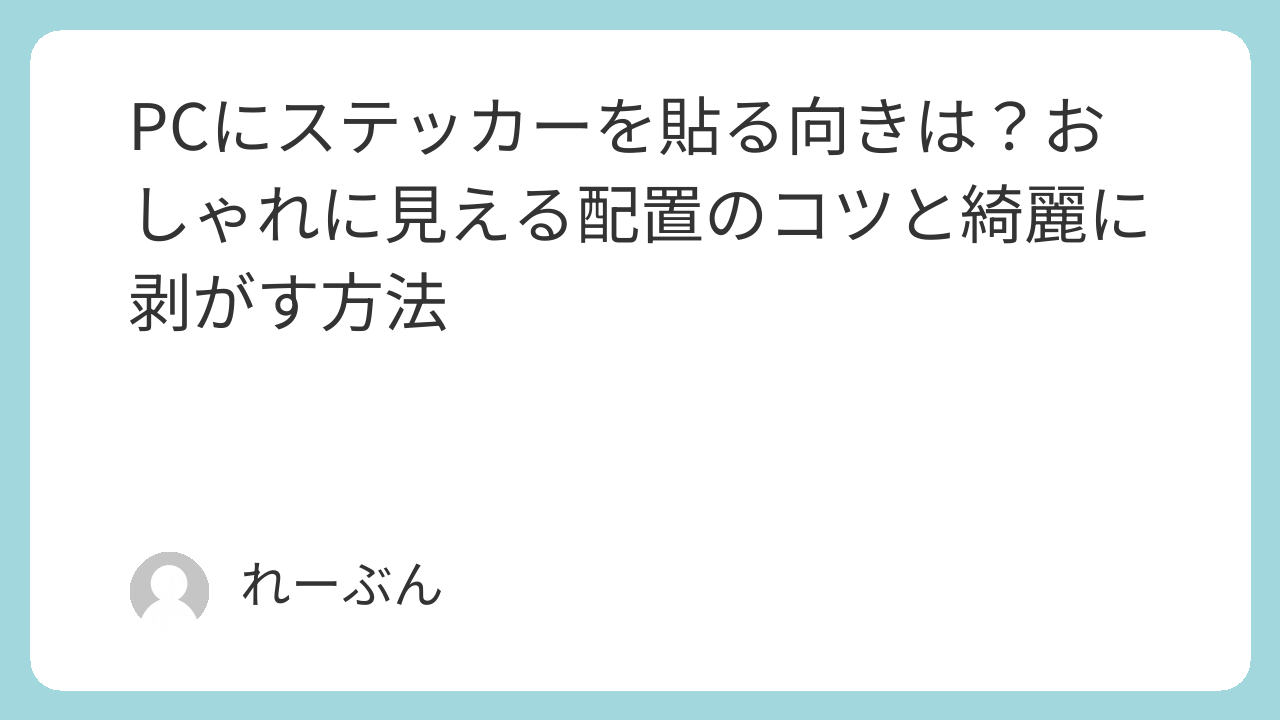パソコンにステッカーを貼ると、いつもの作業時間が少し楽しくなります。 自分らしさをそっと表現できたり、好きなものをそばに置けたりと、気分が上がる小さな工夫です。
でも、貼り方や向きを間違えると「なんだかちょっと思っていたのと違う…」となってしまうこともあります。
このページでは、パソコンにステッカーを貼るときの基本と、センス良く見える貼り方のコツをやさしく解説します。
初心者さんでも大丈夫です。 一緒に、かわいくて整った見た目をつくっていきましょう。
パソコンにステッカーを貼っても大丈夫?まずは注意点

発熱・通気口まわりには貼らない方がいい理由
パソコンは使用中に内部で熱を発生します。
この熱は通気口や放熱部分から外に逃がされる仕組みになっています。
しかし、これらの部分にステッカーを貼ってしまうと、排熱がうまくできなくなることがあります。
すると内部に熱がこもり、パソコンが熱を逃がすためにファンが強く回ることが増えます。
ファンの音が大きくなったり、動作が重くなったりする原因になることがあります。
さらに、長時間熱がこもった状態が続くと、内部パーツが劣化しやすくなります。
結果として寿命が短くなってしまう可能性もあります。
ステッカーを貼るときは、必ず通気口や吸気口の位置を確認し、そこを避けるようにしましょう。
会社PC・学校PCの場合の注意点
会社や学校から支給されているパソコンは、自分が所有しているものではありません。
見た目をかわいくしたい気持ちはあっても、勝手にステッカーを貼ると後で返却するときに問題になることがあります。
特に、剥がしたときに跡が残るタイプのステッカーは注意が必要です。
返却時に「元の状態に戻してください」と言われてしまうと、剥がすのに時間がかかることがあります。
どうしてもデコレーションしたい場合は、パソコン本体ではなくケースやスキンカバーに貼ると安心です。
また、貼ってもきれいに剥がせる「再剥離タイプ」のステッカーを使うのも良い方法です。
中古買取価格に影響する可能性
将来パソコンを手放す可能性がある場合は、ステッカーを直接貼るかどうかを慎重に考えましょう。
ステッカーを剥がしたときに、粘着の跡が残ったり、表面が変色したりすることがあります。
特にマット素材やアルミボディは、跡が残りやすいことがあります。
買取査定では「見た目のきれいさ」が重視されるため、ステッカー跡があるだけで査定額が下がる場合があります。
もし売る予定が少しでもあるなら、本体に直接貼るのではなく、スキンシールやハードケースの上に貼る方法がおすすめです。
その方が、見た目を楽しみつつ価値を保つことができます。
ステッカーが「ダサく見える」原因と回避テク

貼りすぎ / 色がバラバラ / 方向が揃っていない
ステッカーをたくさん貼りすぎると、見た瞬間に「情報量が多い」と感じられやすくなります。
パソコンは面積が広くないため、シールの数が多いほど視線が散り、まとまりがなく見えてしまいます。
色味やサイズがバラバラのまま貼ると、ごちゃっとした印象が強くなり、全体に統一感が出ません。
まずは、貼りたいステッカーを机の上に並べてみましょう。
どのステッカーを主役にするか、その周りにどんなステッカーを添えるかを考えると、バランスが取りやすくなります。
また、向きを揃えるだけでも印象は大きく変わります。
横向きばかりではなく、あえて縦や斜めを混ぜてアクセントにしても可愛いのですが、その場合も「意図的に揃えた配置」にすると、センスよく見えます。
「余白」と「テーマ」を揃えると一気に洗練される
おしゃれに見える貼り方の鍵は「余白」と「テーマ」です。
余白をしっかり残すことで、ステッカーひとつひとつのデザインが際立ち、落ち着きのある仕上がりになります。
逆に、スペースを埋めないと不安に感じてしまったり、全部貼りたい気持ちが先に出てしまうと、ごちゃつきやすくなります。
また、テーマを決めると一気に統一感が生まれます。
テーマ例としては「カフェ風」「モノトーン」「旅行・地図」「動物・推しキャラ」などがあります。
ステッカーの世界観を揃えるだけでも、おしゃれな雰囲気が自然と作れます。
配色とトーンを統一するだけでおしゃれに見える
視覚的なまとまりを作りたいときは、色のトーンを揃えるのがおすすめです。
淡い色で統一すると柔らかく優しい印象に。
モノトーンで揃えるとスタイリッシュで落ち着いた印象になります。
ビビッドカラーは元気でポップな雰囲気になりますが、使いすぎると派手に見えやすいので、ポイント使いにするとバランスよく仕上がります。
色味を「近いもの同士でまとめる」だけでも、全体の調和が生まれ、急に雰囲気がおしゃれに整います。
パソコンにステッカーを貼る前の準備

素材・表面加工で貼りやすさが変わる(アルミ / 樹脂 / マット)
パソコンの天板は、メーカーやモデルによって素材や質感が大きく異なります。
アルミ素材は表面がなめらかで、ステッカーが均一に貼り付きやすいのが特徴です。
一方で、樹脂(プラスチック)製はやや柔らかさがあるため、貼るときに気泡が入りにくい反面、長期間貼ったままだと糊が残る場合があります。
さらに、マット加工やざらつきのある質感は、見た目がおしゃれな反面、ステッカーの粘着が細かい凹凸に入り込みやすいため、剥がすと跡が残ったり、部分的に白っぽくなってしまうことがあります。
貼る前に、指で軽く表面を触ってツルツルかザラザラかを確認し、素材に応じて貼る場所やステッカーの種類を選ぶと安心です。
「剥がす予定がある」「査定に影響させたくない」という場合は、まずクリアケースやスキンシールの上に貼ることで本体を保護できます。
用意すると便利なアイテム一覧(カード / クロス / ピンセット など)
ステッカーをきれいに貼るためには、ちょっとした道具が役に立ちます。
ポイントカードやICカードなどの硬めのカードは、貼るときに中心から外側へ向かって気泡を押し出すのに便利です。
柔らかいクロスは、ステッカーを抑えたり、表面を傷つけずに仕上げるときに重宝します。
小さなステッカーや細かいデザインは、指で扱うと粘着部分に触れて貼りにくくなることがあるため、ピンセットがあると位置調整がとてもスムーズになります。
また、仮置きに使えるマスキングテープがあれば、貼る前に配置を固定でき、ズレを防ぐことができます。
きれいに貼るためのクリーニング手順
ステッカーの密着度を上げるには、貼る前の表面ケアがとても大切です。
油分やホコリが残っていると、はがれやすくなったり、気泡が入りやすくなります。
まずは柔らかい布で軽く表面を拭き、汚れを落としましょう。
可能であれば、シートで皮脂をやさしく取り除きます。
拭いた後は、表面に水分が残らないようにしっかり乾かしてください。
乾いた状態で貼ることで、粘着が安定し、長持ちしやすくなります。
パソコンにステッカーを綺麗に貼る方法

仮置きをしてから位置を決めるコツ
いきなり貼らずに、まずはステッカーをそっと上に置いてみます。
この段階ではまだ貼り付けず、あくまで“置く”だけにするのがポイントです。
全体のバランスや、向き、間隔などを落ち着いて確認できます。
複数の候補位置を試しながら、「どこに置くとかわいく見えるか」を自分の感覚で確認する時間はとても大切です。
マスキングテープを軽く貼って仮固定しておくと、手を離しても見た目をしっかり確認でき、迷いが減ります。
また、写真を撮って客観的に見ると、意外と配置の良し悪しがわかりやすくなるのでおすすめです。
貼る前にイメージを固めておくことで、ズレや貼り直しのリスクをぐっと減らせます。
ゆっくり丁寧に準備することで、仕上がりがぐっときれいになります。
空気を入れない貼り方(カードで中心から外へ)
ステッカーを置いたら、まずは真ん中を軽く押さえて位置を固定します。
そこから、カードを使って中心から外側へ向けて空気を押し出すように滑らせます。
強く押しすぎず、均一な力でじんわり押し広げるイメージです。
このとき、表面をこすりすぎるとステッカーが傷付く場合があるため、やさしく扱うことが大切です。
小さな気泡が残った場合は、端に向かって指でゆっくり押し出してみてください。
もしどうしても抜けない小さな気泡があるときは、つまようじの先で極小の穴を開けて空気を逃がすと、仕上がりがきれいになります。
焦らず落ち着いて、ゆっくり作業することで、見た目がなめらかで美しい仕上がりになります。
複数ステッカーをバランスよく貼るレイアウト術
複数のステッカーを貼るときは、まず一番大きいものや「主役」になるステッカーから貼るのがおすすめです。
大きなステッカーが全体の印象を決めるため、その位置がしっかり決まると、残りのステッカーの配置も自然と決まっていきます。
次に、小さめのステッカーを空いたスペースにリズムよく配置していきます。
このとき、“全部埋めようとしない”ことが洗練された印象につながります。
余白は「センスの余裕」として見えるので、あえて余白を残すことが大人っぽさにつながります。
また、色味や形を近いもの同士でまとめたり、向きを揃えたりすると、全体がすっきり整って見えます。
逆に、少しだけ角度や高さに変化をつけると、アクセントになって遊び心のある雰囲気になります。
見せたい世界観に合わせて調整すると、自然でおしゃれなレイアウトが完成します。
ステッカーの「向き」をどう決める?センスの決め手

開いたとき VS 閉じたとき、どちらを正面にする?
ノートパソコンは、使っているときは開いていますが、机に置いたり持ち運んだりする時間も意外と長いものです。
そのため、どちらの状態で「見せたいか」を基準に向きを決めると、全体の印象が整いやすくなります。
カフェや学校、オフィスで作業をするとき、周りから見えるのは閉じた状態の背面です。
「まわりに見せたい」「推しをアピールしたい」場合は、閉じたときに正面として見える向きがベストです。
一方、自分自身が作業中に気分を高めたい場合は、開いたときに向きが揃うように貼る方法がおすすめです。
誰に向けて見せたいのかを考えると、迷いが少なくなり、自然に向きが決まります。
メーカーのロゴと揃えるとスタイリッシュに見える
パソコンの背面にあるメーカーのロゴは、視線が自然に集まるポイントです。
ステッカーを貼るとき、このロゴの向きと配置に合わせるだけで、統一感が生まれます。
ロゴの上にワンポイントで添えると、控えめで上品な印象に。
ロゴと平行に並べると、整ったまとまりのあるデザインに。
また、ロゴの斜め方向に角度を合わせると、カジュアルでこなれた雰囲気になります。
「ロゴを邪魔せずに活かす」ことで、ブランドの美しさと自分の個性を両立させることができます。
実例|縦置き・斜め配置・ワンポイントの見え方比較
縦向き配置は、落ち着いた整った印象を与えます。
縦にそろうことで視線がまっすぐ流れ、スッキリとした雰囲気になります。
ミニマル系・モノトーン系のステッカーとの相性がとても良いです。
また、ノートパソコンを縦置きスタンドに立てることが多い方は、縦向きに貼ると見え方がより自然になります。
シンプルに見せたい、静かなデザインにまとめたい人に向いています。
斜め配置は、少し動きのあるアクセントを作りたいときに最適です。
まっすぐではなく、意図的に角度をつけることで「余裕」や「こなれ感」が生まれます。
ラフでかわいい印象になり、親しみやすさが出る貼り方です。
カジュアルなお洋服や、クリエイティブな雰囲気が好きな人によく似合います。
ステッカーを複数貼るときは、斜め方向に沿って並べるとリズム感が出ておしゃれに見えます。
ワンポイント配置は、余白そのものをデザインとして活かす貼り方です。
小さめのステッカーをひとつだけ、ロゴの近くや端にさらっと添えると、とても洗練された印象になります。
静かで大人っぽい雰囲気が生まれ、「ちゃんと選んだ感」が伝わりやすいのも魅力です。
シンプル派・上品さを重視したい人におすすめです。
また、複数のステッカーを貼るときでも、「主役のステッカーをひとつ決める」ことで、全体がすっきりとまとまります。
主役を中心に、サブのステッカーを少し離して配置すると、メリハリのあるレイアウトになり、視線の流れもきれいに整います。
「どこを見てほしいか」を意識することで、貼り方のセンスがぐっと上達します。
ステッカーのテーマを決めると世界観が整う
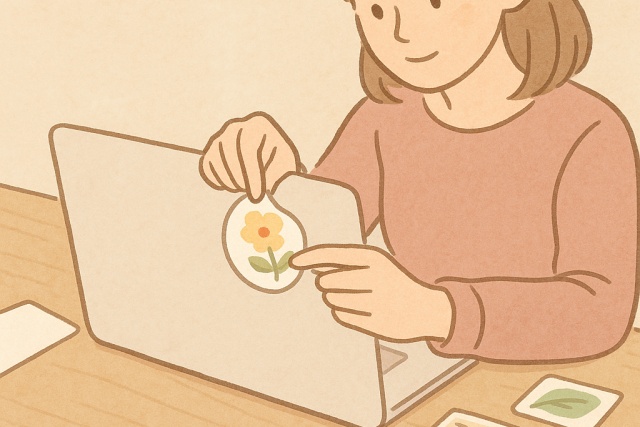
テーマを最初に決めると、統一感が出てぐっとおしゃれに見えます。
自分の「好き」をじっくり思い出しながら、方向性を決めていきましょう。
ミニマル / かわいい / カフェ・雑貨感 / 海外スケーター風
どの雰囲気が好きかをまず選んでみましょう。
自分の普段の持ち物や洋服の系統を思い出すと、しっくりくるテイストが見つかれます。
白や黒のシンプル系ならミニマルにまとめると、落ち着いた大人っぽい雰囲気になります。
カフェ・雑貨感が好きな方は、クリーム色・ブラウン・生成りなど、やさしい色を取り入れると統一感が生まれます。
かわいい系なら、キャラクターや手描き風のラインアート、丸みのある文字などがしっくりきます。
海外スケーター系は、ステッカーをたっぷり貼るのが特徴なので、にぎやかで「動き」を感じる仕上がりになります。
少し重ね貼りしたり、斜めに貼ると、ラフでこなれた印象になります。
推し・旅行・ブランドで統一すると印象が強まる
「推しの名前」「旅行先のステッカー」「好きなブランドのロゴ」など、共通点を作ると世界観がまとまります。
同じテーマでそろえることで、見たときに感じるまとまりや、一貫した雰囲気が自然に生まれます。
たとえば旅行なら、海外のカフェやホテルで配られているステッカー、旅先の名物を描いたイラストステッカーなどを集めるだけでも、PCがちいさな旅の思い出アルバムのようになります。
推し活なら、推しカラー・曲名・シンボルマークなど、モチーフに統一感を持たせるのがおすすめです。
カラーがそろうと、控えめでもしっかり“推してる感”が出せます。
ブランド系で統一する場合は、ロゴの大小・配置のバランスを調整すると、上品で洗練された雰囲気になります。
見た人に「これ好きなんだな」と伝わりやすくなり、自分の気持ちにも一層なじみます。
気分が落ちた日でも、PCを開いたときにすぐ元気を届けてくれる“お守り”のような存在になることもあります。
「色・質感・厚み」を揃えるとプロっぽい見た目に
同じような素材で揃えると、見た目がとてもキレイに整います。
マット系ならマットで統一、ツヤありならツヤありでそろえると、雑多に見えません。
「質感の統一」は意外と見た人の印象に大きく関わる部分で、ここがそろうだけでおしゃれ度が一段アップします。
また、厚みがそろっていると、貼った面に段差が少なくなり、自然でなめらかな仕上がりになります。
触れたときにゴツゴツせず、長く使ってもはがれにくいのもメリットです。
シール同士がぶつかったり浮いたりしないので、仕上がりが“最初からそうデザインされていたように”見えます。
「貼るだけ」なのに、丁寧にデザインされたような洗練された雰囲気が出せる、簡単だけど効果の高いテクニックです。
「色・質感・厚み」を揃えるとプロっぽい見た目に
同じような素材で揃えると、見た目がとてもキレイに整います。
マット系ならマットで統一、ツヤありならツヤありでそろえると、雑多に見えません。
素材感の統一は、意外と“おしゃれに見えるポイント”の大部分を占めています。
厚みもそろうと、表面に段差が少なくなり、手触りも滑らかになります。
シール同士がぶつかりにくいため、はがれにくく実用面でも安心です。
上手に選ぶことで、まるで最初からデザインされていたかのような、自然な仕上がりになります。
推し・旅行・ブランドで統一すると印象が強まる
「推しの名前」「旅行先のステッカー」「好きなブランドのロゴ」など、共通点を作ると世界観がまとまります。
同じジャンルやテーマでそろえることで、ステッカー同士がけんかせず、自然とまとまりある仕上がりになります。
たとえば旅行系なら、「空港ラベル風」「国旗」「旅先の地図柄」「ホテルのロゴ風」などの組み合わせがおすすめです。
過去の旅行の思い出をPCの上に並べることで、見るたびにワクワクした気持ちがよみがえるかもしれません。
推し活の場合は、「ライブのロゴ」「カラーの統一」「モチーフのシルエット」など、想いをさりげなく詰め込むのがポイントです。
他人に見せるというよりは、自分自身の気持ちを高める“お守り”として活用するのも素敵です。
ブランド系でまとめるなら、「色味」「ロゴの大きさ」「配置のリズム」に注目すると、洗練された印象に。
並べる順番や向きにこだわることで、プロがレイアウトしたような一体感が出せます。
見た人に「これ好きなんだな」と伝わりやすくなり、自分の気持ちにも一層なじみます。
そして、毎日使うパソコンを開いた瞬間に、自分の“好き”がぎゅっと詰まった空間が目に入ると、自然と気分が上がります。
「色・質感・厚み」を揃えるとプロっぽい見た目に
同じような素材で揃えると、見た目がとてもキレイに整います。
素材に統一感があることで、ステッカーがそれぞれ主張しすぎることなく、全体としてまとまりのある印象になります。
マット系ならマットで統一、ツヤありならツヤありでそろえると、視線が分散せず落ち着いた見た目になります。
質感がそろうだけで、“整っている”と感じる視覚効果があり、全体的に洗練された印象になります。
また、厚みもそろうと、貼ったときの段差が少なくなり、触ったときにも違和感がありません。
ゴツゴツ感や引っかかりがなくなることで、カバンにしまうときや持ち運ぶときもスムーズにいきます。
一枚一枚のシールがきちんとおさまっている感じがして、結果的に長持ちしやすいというメリットも。
こうした小さな気遣いが、プロっぽく見えるコツのひとつです。
「貼るだけ」で終わらず、“仕上がり”を意識するだけでワンランク上の雰囲気が手に入ります。
PCの色別|相性の良いステッカーデザイン
パソコンの本体の色と相性を考えると、自然にまとまります。
持っているPCの色に合わせて選んでみましょう。
シルバーPC → 透明系 / モノトーンが馴染む
シルバーはどんな色にも合わせやすい万能タイプです。
どんなテイストのステッカーでも比較的なじみやすく、自由なアレンジが可能です。
透明ベースのステッカーを貼ると、「浮かない」自然な雰囲気に仕上がります。
ステッカーの色や形がそのままきれいに見えるのもシルバーならではの強みです。
モノトーンでまとめると、スタイリッシュで大人っぽい印象に。
黒・白・グレーなどのシンプルな色合いが引き立ち、無機質な雰囲気もおしゃれに見えます。
文字やロゴだけのデザインなら、さりげなさと高級感を両立できます。
黒・ダーク系 → カラーアクセントが映える
黒やダークグレーのPCには、鮮やかな色がよく映えます。
背景が暗いぶん、色味のあるステッカーはより一層はっきりと見えます。
レッド、イエロー、ブルーなど、ポイントになる色を少し入れるとおしゃれです。
派手すぎるのが苦手な人は、ステッカーの面積を小さめにして取り入れるとバランスよくまとまります。
落ち着かせたい場合は、シンプルな白文字ステッカーも相性抜群です。
黒地に白のロゴやワンポイントは、洗練されたミニマルな印象になります。
少ない枚数で印象を変えたい方におすすめのスタイルです。
パステルPC → 淡色×淡色でやさしくまとまる
パステルカラーのPCは、淡い色でトーンを揃えると、やさしく統一感のある印象になります。
彩度の高い色よりも、生成り・くすみカラー・ソフトなトーンを選ぶとまとまりが出ます。
ミルク系カラーや透明感のある素材だと、かわいらしくも上品に仕上がります。
くもりガラス風や淡い水彩タッチのデザインは、パステルPCとの相性が抜群です。
ふんわりとした印象にしたい場合は、丸みのあるデザインや線の細いモチーフを選ぶとより優しい仕上がりになります。
「見せすぎないおしゃれ」がしたい方にぴったりです。
控えめにしたい人へ|バレにくいおしゃれな貼り方
「ごちゃごちゃさせたくない」「仕事や学校で派手に見せたくない」という方でも大丈夫です。
控えめでも十分かわいく見せられます。
透明ステッカーで“さりげなく”
透明ステッカーは、本体の色が生きるので目立ちすぎません。
色の主張が少ない分、落ち着いた印象に仕上がり、職場や学校でも使いやすいのが魅力です。
透け感があることで、下地の色や質感と自然に馴染み、まるで本体の一部のような仕上がりになります。
さりげなく好きなモチーフや言葉を入れたい方にぴったりで、見るたびに小さな喜びを感じられます。
やわらかい雰囲気で、上品に個性を出せます。
また、透明な素材は比較的はがれにくく、長くきれいな状態を保てるのもポイントです。
小さいワンポイントだけで雰囲気を変える
大きなステッカーを貼らなくても、角に小さなマークや文字を置くだけでも雰囲気が変わります。
ほんの少しのアクセントで、「あれ、なんかかわいい」と感じさせることができます。
星やハート、小さな花やシンプルなロゴなど、自分の気分に合わせて選ぶと気分転換にもなります。
「ちょっと気分を変えたい」くらいの人にぴったりです。
貼る位置を右上・左下など決めておくと、見た目にもバランスが取れて見えます。
PCケースに貼れば「剥がせる」&安心
本体に直接貼るのが不安な場合は、ケースに貼るのがおすすめです。
最近では透明のPCケースも豊富にあるので、本体の色やロゴを活かしながらステッカーを楽しめます。
ケースに貼れば、万が一デザインに飽きてもケースごと変えられるので、貼り替えも簡単です。
シール跡を残したくない人や、気分でデザインを変えたい人にぴったりの方法です。
季節やイベントに合わせてステッカーを変える“着せ替え感覚”も楽しめます。
気分が変わればケースごと変えられるので、ダメージもありません。
剥がせるステッカーの貼り方と再利用テク
貼るときにひと工夫をしておくと、後でキレイに剥がせます。
「あとで変えたくなるかも」という方にぴったりです。
マスキングテープを“下地”にする方法
ステッカーを直接貼らず、下にマスキングテープを貼ってから重ねます。
こうすると簡単に剥がせて、跡も残りません。
特に大切なPCや、表面に傷をつけたくない人にとっては安心な方法です。
マスキングテープは文房具店や100均でも手軽に手に入るので、気軽に試せます。
柄入りのマステを使えば、下地そのものもデザインの一部として楽しめます。
さらに、マステを土台にしておくことで、ステッカーの貼り直しや配置の微調整もしやすくなります。
一度貼ってから気に入らなかった場合も、やり直しが簡単にできるのが魅力です。
再剥離タイプ / 静電吸着タイプの特徴
再剥離タイプは、何度でも貼り替えできるシールです。
粘着力が弱めに設計されているので、はがすときにベタつきが残りにくく、本体にも優しいのがポイントです。
静電吸着タイプは、粘着剤を使わずにくっつくので、PCにやさしい仕様です。
静電気の力でパチッと吸着する仕組みで、まるで画面保護フィルムのように何度も使えるのが魅力です。
どちらも、貼ることに慎重になりすぎなくていいため、ステッカーデビューの方にもぴったりです。
粘着力を軽くする裏ワザ(指で軽くなじませる)
貼る前にシール面を指で少し触れると、粘着がほんのり弱まって剥がしやすくなります。
貼ったあとに「やっぱりここじゃなかったかも」と感じることがある方には、とても便利なテクニックです。
指で軽くなじませる程度なら粘着力を極端に損なうことなく、剥がしたときの跡残りも減らせます。
洋服や布の上に一度ペタッと貼ってから使う人もいて、それも粘着を弱める方法として効果的です。
貼り直しの予定がある時におすすめです。
パソコンのステッカーを綺麗に剥がす方法
時間がたったステッカーでも、手順を守ればきれいに取れます。
焦らず、ゆっくり作業するのがコツです。
ドライヤーを使ってゆっくり剥がす
温風を当てると粘着剤が柔らかくなり、剥がしやすくなります。
ステッカーの端を少しずつ持ち上げながら、じんわり温めるのがコツです。
勢いよく引っ張ると、ステッカーがちぎれたり、粘着が残ったりすることがあるので注意しましょう。
引っ張らず、端から少しずつゆっくりめくり上げるのがポイントです。
温風は少し離して当てることで、PC本体へのダメージも防げます。
冬場や乾燥しているときは粘着が硬くなりやすいため、ドライヤーの活用が特におすすめです。
シール剥がしスプレーの使い分け
粘着が残ったら、シール剥がしスプレーが便利です。
ステッカーをはがした後のベタベタにスプレーを吹きかけ、数秒置いてからやわらかい布でふきとります。
手元になければ、ウェットティッシュなどでもOKです。
ただし、刺激が強いので、PCの素材や塗装によっては色落ちすることもあるため、目立たない場所でテストしてから使いましょう。
ベタベタを残さない最終クリーニング
最後にやわらかい布で表面をふきとると、元のツルッとした質感が戻ります。
クリーニングクロスや眼鏡ふき用のマイクロファイバーなどが適しています。
無理にこすらず、やさしく仕上げましょう。
細かい粘着がまだ残る場合は、テープでペタペタと軽く取り除くのも効果的です。
すべてきれいに取り除けたら、仕上げに乾拭きして、ホコリを防止しましょう。
おしゃれなステッカーが買えるおすすめショップ
ステッカーは身近なお店でも通販でも手に入ります。
テイストに合わせて探してみましょう。
Amazon / 楽天で買える人気セット
いろいろなデザインがまとまったセットが多く、種類を試しやすいです。
たとえば「動物モチーフ」「レトロポップ系」「英字ロゴ風」など、ジャンル別に分かれているセットもあります。
価格もお手頃なものが多く、初心者の方が気軽にチャレンジするのにぴったりです。
気分や季節でステッカーを入れ替える楽しみ方をしたい方にもおすすめです。
枚数が多めなので、お友達とシェアしたり、スマホやノートに貼っておそろいにしても楽しいですね。
気軽に楽しみたい方に向いています。
LOFT・ハンズ・無印で買える控えめ系
落ち着いたニュアンスや、シンプルで洗練されたデザインが揃います。
透明ステッカーや、色味をおさえたナチュラル系のモチーフが多く、どんなPCにも合わせやすいです。
派手さを抑えつつも、ほんのり個性を出したいという方にぴったりです。
仕事用PCにもなじみやすいですし、上司や同僚の視線も気にせず使える安心感があります。
文房具好きな方は、文具売り場でついでに探してみるのも楽しい時間になります。
海外デザイナー系なら「Etsy」がおすすめ
個性的で、アートのようなステッカーがたくさん見つかります。
手描き風イラスト、ビンテージ風デザイン、抽象的なアートなど、他では見つからないユニークな作品が揃っています。
海外の作家さんから直接購入できるので、世界にひとつだけの雰囲気を楽しみたい人にぴったりです。
英語の表記が多いですが、最近では日本向け発送対応のショップも増えていて、安心して利用できます。
海外の雰囲気をパソコンに取り入れたい方にはとくにおすすめです。
まとめ|お気に入りのステッカーでパソコンをもっと自分らしく
パソコンは毎日目にするものだからこそ、自分の「好き」をのせてあげたいですね。
大げさじゃなくても、ちいさなステッカー一枚で気分は大きく変わります。
あなたの心がふわっと嬉しくなるようなデザインを選んで、日常をもっと心地よくしてみてくださいね。