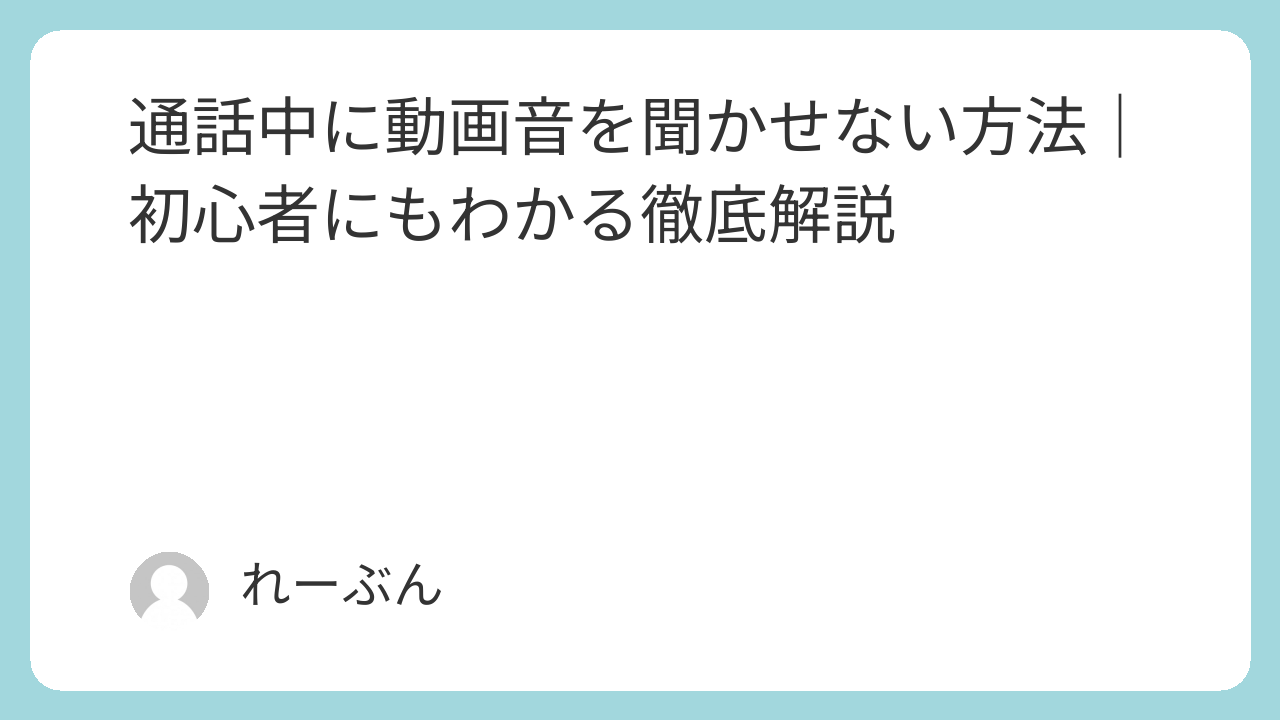通話をしているときに、うっかり動画を再生してしまい「相手に音が聞こえていないかな?」と不安になったことはありませんか?
特にリモート会議や大事な電話の最中に動画の音が混ざると、相手に迷惑をかけてしまうだけでなく、自分も会話に集中できなくなってしまいます。
そこで今回は、スマホ・PC・アプリごとにできる音漏れ防止策をわかりやすく解説します。
初心者の方や機械にあまり詳しくない方でも実践できるように、具体的な設定方法やちょっとしたマナーの工夫も紹介しているので、安心して読み進めてくださいね。
通話中に動画の音が相手に聞こえるのはなぜ?

マイクとスピーカーの仕組みを知ろう
スマートフォンやパソコンには、私たちの声や周囲の音を拾うためのマイクと、音楽や通話の音を出すスピーカーがそれぞれ内蔵されています。
この2つの機能はとても便利ですが、実は通話中には意図しない音まで相手に届けてしまうことがあるのです。
特に、マイクは声だけでなく環境音も拾ってしまう性質があるため、静かな環境でなければ背景の音までしっかり伝わってしまいます。
動画を視聴している場合、その音もマイクが拾ってしまい、通話相手に音が聞こえてしまうのはこの仕組みによるものです。
さらに、マイクは自分の声を拾いやすくするために感度が高く設定されていることが多く、結果として思った以上に周囲の音を拾ってしまう原因になります。
音が通話に乗る原因とは?
音漏れが起きる理由はひとつではありません。
まず、スピーカーの音量が大きすぎると、その音が直接マイクに届きやすくなり、結果として相手に音が伝わってしまいます。
スピーカー通話をしていると、音の出る場所と音を拾う場所が近いため、特に音漏れが発生しやすくなります。
また、静かな場所にいないと背景音が強調されてしまい、動画の音や雑音がより相手に響いてしまうこともあります。
このような環境要因も音漏れの大きな原因の一つです。
加えて、端末の設定によってはマイクの感度が高くなっている場合もあり、必要以上に周囲の音を拾ってしまうことがあります。
通話アプリの仕様によっては防げないこともある
さらにややこしいのが、使用する通話アプリの仕様によっては、動画の音を完全に遮断できないケースがあるという点です。
たとえば、一部の通話アプリでは、システム全体の音声を通話に混ぜてしまう仕様になっており、別のアプリで再生された音声も一緒に相手に送られてしまうことがあります。
また、マルチタスク中の音声制御が甘いアプリでは、動画の音声や通知音がそのまま通話に乗ってしまうこともあります。
こうした仕様はユーザー側では設定変更できないこともあるため、どのアプリを使うかによっても音漏れリスクは変わってきます。
したがって、事前にそのアプリの仕様や設定方法を確認し、必要であれば代替手段を検討することも大切です。
音漏れを防ぐ基本対策とマナー

イヤホン・ヘッドセットを使うべき理由
イヤホンやヘッドセットは、通話中の音漏れを防ぐための基本的なアイテムとして非常に有効です。
スピーカーを使った通話では、音がそのまま外部に漏れやすくなり、その音がマイクに拾われて相手に届いてしまうことがよくあります。
しかし、イヤホンを使用することで、音声は直接耳元で再生され、マイクに入り込むことがなくなるため、通話相手に余計な音を届けずにすみます。
特にマイク付きのイヤホンやヘッドセットは、自分の声をピンポイントで拾いやすく、周囲の雑音を拾いにくい設計になっているため、クリアで聞き取りやすい通話が可能になります。
また、ヘッドセットにはノイズキャンセリング機能を搭載しているモデルもあり、さらに雑音をカットする効果が期待できます。
通話の品質を保つためにも、なるべくスピーカー通話は控え、信頼性のあるイヤホンやヘッドセットを日常的に活用することをおすすめします。
音量・環境を見直してトラブル防止
動画の音量を必要以上に大きくすると、イヤホンを使っていても周囲に音が漏れてしまうことがあります。
とくに感度の高いマイクを使用している場合、音が小さくても拾ってしまう可能性があるため、通話中は再生音量を抑えめに設定することがポイントです。
さらに、通話する環境も非常に重要です。
窓の近くや換気扇の下、テレビのついている部屋など、ノイズが入りやすい場所を避けて静かなスペースを選びましょう。
外出先で通話する場合も、できるだけ人通りの少ない場所を探すことで、より安定した通話品質を保つことができます。
このように音量と環境の見直しを意識するだけで、通話中のトラブルを未然に防ぐことができ、相手にとっても快適な時間を提供できます。
相手に不快感を与えないマナーと注意点
通話中に突然別の音が混ざると、相手に不快感を与えるだけでなく、内容の聞き取りに支障が出ることもあります。
とくに動画の音や通知音は急に大きな音で流れることがあるため、通話前に確認や準備をしておくことが大切です。
「ちょっと動画を確認するね」「音が出るかもしれないけどすぐ戻すね」といった一言を添えるだけで、相手の印象は大きく変わります。
ビジネスや目上の方との会話であれば、特に丁寧な配慮が求められます。
また、相手が話している最中に音がかぶるのは失礼にあたることもあるため、タイミングを見て行動することもマナーのひとつです。
万が一漏れたときのフォロー方法
どれだけ注意していても、うっかり音が漏れてしまうことはあります。
そんなときは、素直に「ごめんね、ちょっと動画の音が入っちゃったかも」と謝るだけでも印象が大きく変わります。
すぐに音を止めたり、再生を中断するなど、誠意をもって対応する姿勢が大切です。
さらに、「次から気をつけるね」「急ぎで確認したくてごめんね」といった言葉を添えると、より丁寧な印象になります。
音漏れは相手の集中力を削いだり、不快な気持ちを与えたりする原因になりかねませんが、しっかりとしたフォローで信頼関係を保つことができます。
こうしたちょっとした気配りが、より良いコミュニケーションにつながります。
スマホでの音漏れ対策(iPhone・Android)

iPhoneでの設定手順と音声制御のコツ
iPhoneでは「設定」アプリから「アクセシビリティ」>「オーディオ/ビジュアル」>「モノラルオーディオ」「ヘッドフォン調整」「バックグラウンドサウンド」など、音に関する詳細な調整が可能です。
たとえば「モノラルオーディオ」をオンにすると左右の音が統一され、片方のイヤホンしか使えないときでも相手の声をしっかり聞き取れるようになります。
また「ヘッドフォン調整」では、自分の聴力や好みに合わせて音声の出力バランスをカスタマイズできるので、必要以上の音量を出さずに済み、音漏れのリスクも下げられます。
「画面収録」機能を利用する際には、コントロールセンターからマイク音声のオン/オフを事前にしっかり確認しましょう。
また、通話中に音楽アプリやYouTubeの音が誤って流れないよう、アプリのミュート設定や通知制御も併せてチェックするのがポイントです。
iOSの「集中モード」を活用して、通話中に関係のない通知や音が入らないよう設定しておくと、より安心して通話ができます。
Androidでアプリごとに音を切る方法
Androidでは端末やOSのバージョンによって多少異なりますが、基本的に「設定」>「サウンドとバイブ」や「アプリ」>「通知」から、各アプリの通知音やメディア音を個別に制御することができます。
たとえば通話アプリだけを優先的に使いたい場合、他のエンタメ系アプリの音をミュートにしたり、通知をオフにすることで、通話に集中しやすくなります。
また、Samsung製端末などでは「サウンドアシスタント」などの専用アプリを使うことで、音の出力先や音量をより細かく設定することも可能です。
一部端末では「マルチオーディオ制御」が使えるため、たとえば音楽をBluetoothで再生しつつ、通話は本体マイクというような使い分けもできます。
こうした機能を活用すれば、意図しない誤再生を防ぎつつ、より快適に通話を楽しむことができます。
通話中にYouTubeなどを再生したいときの裏ワザ
イヤホンやBluetooth機器を装着し、音声出力を完全に耳元に閉じ込めることで、通話相手に動画の音が聞こえないようにすることが可能です。
加えて、Androidではマルチウィンドウ機能を使うことで、画面の半分で通話アプリを開いたまま、もう半分で動画を再生することができます。
また、iPhoneや対応Android機種では「PIP(ピクチャー・イン・ピクチャー)」機能を使うことで、通話中でも画面の片隅で動画を小さく再生し続けられるので便利です。
YouTube Premiumユーザーであれば、バックグラウンド再生にも対応しているため、動画の音だけをイヤホンで聞きつつ、通話に集中することもできます。
ただし、PIP機能はアプリによって制限されていたり、OSのバージョンが古いと使えない場合もあるため、事前に端末やアプリの対応状況を確認しておきましょう。
Bluetoothイヤホンでの高度な対策
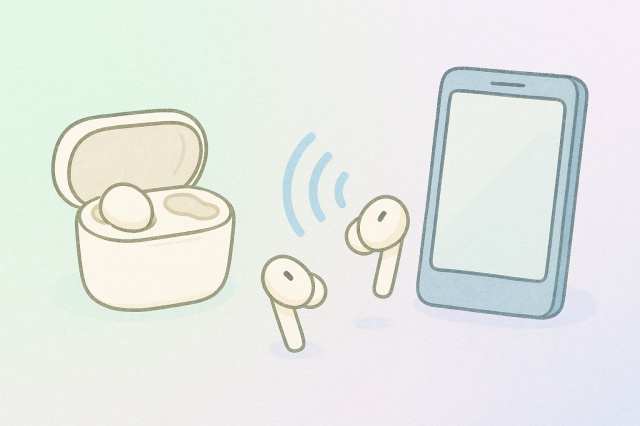
ノイズキャンセリング機能の実力とは
Bluetoothイヤホンの中には、周囲の騒音を自動的に検知し、反対の音波を発生させることで雑音を打ち消す「ノイズキャンセリング機能」が搭載されている製品があります。
この機能は特に外出時や公共の場所など、周囲にさまざまな音がある環境で非常に役立ちます。
たとえば、電車内の走行音やカフェのざわめきなどを効果的にカットすることで、通話時に自分の声だけが相手にクリアに届きやすくなります。
また、ノイズキャンセリングはイヤホン本体のマイクにも影響を与え、不要な周囲の音をマイクが拾わないようにする働きもあるため、音漏れ対策だけでなく、通話の品質向上にもつながります。
通話に特化したノイズキャンセリング機能を搭載している製品を選ぶと、より高い効果が得られるでしょう。
マイク感度を調整できるおすすめアプリ
スマートフォンで使用するマイクの感度を細かく調整したい場合には、専用のアプリを活用するのが便利です。
Android端末では「SoundAbout」や「Lesser AudioSwitch」などのアプリを使うことで、音声入力のデバイス選択や感度調整が可能となり、余計な音を拾わないよう最適な環境を整えることができます。
これらのアプリは通話中にマイクの感度が高すぎて周囲の雑音を拾ってしまう場合や、逆に声が小さくて聞こえづらいときなどにとても役立ちます。
ただし、端末のメーカーやOSバージョンによっては一部機能が使えなかったり、正常に動作しないこともあるため、導入前にアプリのレビューや対応機種情報をチェックすることをおすすめします。
iPhoneではシステムレベルでのマイク感度調整は限定されていますが、オーディオ関連の設定や録音アプリを活用して調整することも可能です。
Bluetoothの接続トラブルを防ぐ設定
Bluetoothイヤホンが通話中に接続不良を起こすと、音声が途切れたり雑音が入ったりする原因となり、結果的に音漏れや誤解の元になることがあります。
安定した通信環境を保つためには、定期的にBluetooth接続の履歴(ペアリング情報)をリセットしたり、端末のBluetoothキャッシュを削除するのが効果的です。
また、複数のBluetooth機器と同時に接続していると、通信が不安定になったり、誤作動を起こすことがあります。
使用していないBluetooth機器の接続を解除する、通信範囲内にある他の機器との干渉を避けるなどの工夫も有効です。
さらに、Bluetoothイヤホンのファームウェアを最新バージョンにアップデートすることで、接続の安定性や音質が向上することがあります。
定期的なアップデート確認も忘れずに行いましょう。
通話アプリ別の音声コントロール方法

LINE通話で音漏れを防ぐ設定
LINEアプリでは、通話設定から「通話中に他のアプリの音を再生しない」オプションをオンにすることで音漏れを軽減できます。
この設定を有効にしておけば、通話中に誤って音楽や動画を再生してしまっても、相手に直接音が伝わりにくくなります。また、通話画面にある「スピーカー」や「マイク切り替え」なども活用して、状況に応じて最適な切り替えを行いましょう。スピーカー通話からイヤホン通話へすぐに変更するなど、臨機応変な対応ができると安心です。
さらに、LINEの最新版ではノイズ抑制機能が強化されており、環境音が入りにくいよう設計されています。アプリを常にアップデートしておくことも、音漏れ防止に役立ちます。
Zoom・Skype・Google Meetでの詳細設定
ZoomやSkype、Google Meetでは、音声の入力デバイスや出力デバイスの選択が可能です。USBマイクや外付けスピーカーを利用している場合も、設定画面で自由に切り替えができます。
設定画面からマイク感度の自動調整をオフにしたり、エコー除去機能を活用したりすることで、通話品質を改善できます。さらに「雑音抑制」や「ステレオ音声を有効にする」といった詳細オプションも使えば、会話音と背景音をよりはっきり分けられます。
バックグラウンドでの音声再生を避けることも大切で、不要な通知音やシステム音が混ざらないようにアプリの通知設定も調整しておくと、より快適な会話が可能になります。
通話アプリ別|音声制御機能の違いを比較
LINEは簡易的な設定が多い一方で、ZoomやSkypeは詳細な音声制御が可能です。
たとえばZoomでは「オリジナルサウンド」機能を有効にすると、マイクの音が加工されずにそのまま伝わるため、音楽演奏やプレゼンに向いています。一方でSkypeはエコーキャンセルや自動音量調整がしっかりしており、初心者でも使いやすいのが特徴です。
また、アプリによってはマイクとスピーカーの同時使用に制限があるため、自分の利用目的に合ったアプリを選ぶこともポイントです。例えばGoogle Meetはブラウザ版でも細かく設定でき、ビジネス用途に便利です。
音質・利便性・プライバシーのバランスを考えて選択しましょう。
パソコンでの通話×動画音声の分離方法
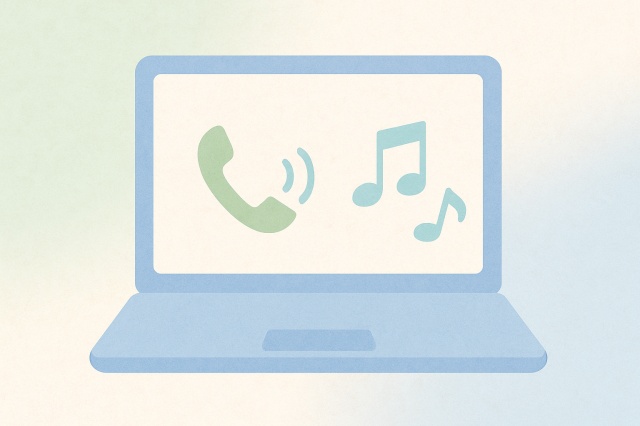
Windowsでマイクと出力を別々に管理する
Windowsでは「サウンド設定」や「コントロールパネル」から、アプリごとに出力先やマイクを切り替えることができます。これにより、通話と動画の音声を完全に別経路に振り分けられるため、相手に不要な音を聞かせずに済みます。
たとえば、通話はUSBヘッドセットを指定し、動画音声はスピーカーや外付けオーディオ機器に出すといった使い分けが可能です。
さらに、Windowsの「アプリごとの音量とデバイス設定」機能を利用すれば、特定アプリだけの音声を特定デバイスに割り当てられるので、より自由度の高い環境を作れます。
また、「サウンドミキサー」や「Voicemeeter」などの仮想オーディオミキサーを導入することで、マイクと出力のルーティングを細かく制御することができます。これを使えば、通話相手には声だけを届けつつ、動画音声は自分の耳にだけ届くように設定できるなど、プロ並みの分離が可能です。
最初は設定が複雑に感じるかもしれませんが、一度慣れると非常に便利で、ビジネス会議や配信などでも重宝します。
Macで通話音声と動画音声を切り離す方法
Macの場合、「Audio MIDI設定」や「BlackHole」「Loopback」などの仮想オーディオデバイスを使えば、音声のルーティングを細かくコントロールできます。例えば、通話アプリの音声をヘッドセットに、動画の音をスピーカーに分けるといった設定が可能です。
この方法により、通話と動画の音声を完全に別々の出力に振り分けることができ、相手に動画音声が届く心配がなくなります。
設定に多少時間がかかりますが、一度覚えてしまえば日常的に快適に活用でき、ビデオ会議やオンライン授業などにも役立ちます。
PCとスマホを併用して音漏れを防ぐテク
PCで通話をしながら、スマホで動画を視聴する方法も有効です。この場合、通話と動画再生が完全に別のデバイスになるため、音漏れリスクがほぼゼロになります。
Bluetoothイヤホンをスマホに接続し、PCではマイク付きヘッドセットを使えば、快適な二刀流スタイルが実現します。
さらに、スマホ側で音楽や動画を再生しつつ、PCでは会議や授業に集中できるため、作業効率もアップします。必要に応じて音量を調整することで、相手に迷惑をかけず自分も楽しめる理想的な環境を構築できます。
音漏れ防止に役立つ便利アプリ・ソフト
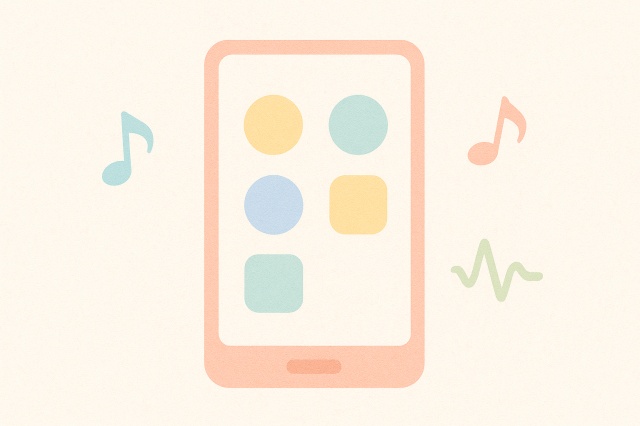
無料で使えるおすすめアプリ3選
-
SoundAbout(Android)
-
Krisp(Windows/Mac)
-
Voicemeeter(Windows)
これらのアプリやソフトは、マイク制御や音声分離に役立ちます。
たとえばKrispはAIを使ったノイズキャンセリング機能があり、キーボードのタイピング音や環境音を効果的にカットできます。Voicemeeterは仮想オーディオミキサーとして有名で、複数の音声を自在にルーティングできるため、配信者や在宅ワーカーにも人気です。SoundAboutは古いAndroid機種でもマイクと出力を柔軟に切り替えられる便利なアプリです。
無料でも十分使える機能が揃っているので、まずは試してみるのがおすすめです。必要に応じて有料版や拡張機能を導入すれば、さらに高性能な音声制御環境を構築できます。
導入前に知っておきたい設定と注意点
アプリやソフトを導入する際は、使用端末のOSバージョンや対応状況を事前に確認しましょう。古いバージョンのOSでは最新機能が使えないこともあり、互換性に注意する必要があります。
また、設定を間違えると逆に音が入らなくなることもあるため、初期設定は慎重に行うのがポイントです。
例えばVoicemeeterの設定は少し複雑ですが、公式チュートリアルを参照すれば迷わず導入できます。マニュアルや公式サイトの解説を参考にしながら操作することを習慣づけましょう。
アプリの組み合わせで逆効果になるケースも
複数の音声系アプリを同時に使うと、設定が競合して不具合が起きることがあります。たとえば、ノイズ除去とエコーキャンセルが重複すると音が聞こえづらくなるなどの現象です。
さらにCPUやメモリの負荷が増えて端末の動作が重くなることもあるため注意が必要です。
1つずつ順番に導入して、問題が起きないか確認しながら使うようにしましょう。安定して使える環境が整ったら、そのまま継続するのが安心です。
ゲーム実況・配信通話中の音漏れ対策

Discord・OBS・Twitchの設定ポイント
Discordでは「ユーザー設定」>「音声・ビデオ」で、入力感度の自動調整やノイズ抑制を有効にすると音漏れを軽減できます。
さらに、マイクテスト機能を使って自分の声がどう相手に聞こえているか確認しておくと安心です。通話に不要なバックグラウンド音を拾わないように、エコー除去や音声検出のしきい値を細かく調整しておくことも効果的です。
OBSでは音声ミキサーで通話音とゲーム音を分け、配信に含める音を選択できます。音声フィルターを使えば、ノイズゲートやコンプレッサーの調整により配信音質を大幅に改善することができます。
また、シーンごとに音声設定を変えることで、雑談シーンとゲームプレイシーンで異なる音声環境を実現でき、よりプロフェッショナルな配信が可能になります。
Twitchも配信ソフトを併用すれば、細かい音声設定が可能です。OBSやXSplitなどの外部ツールを使うと、音量バランスを個別に調整したり、音声フィルターを追加して音質を向上させることができます。
さらに、Twitchの拡張機能を利用すれば、視聴者にとって聞き取りやすい環境を作ることも可能です。
ゲーム音と通話音を分けて配信する方法
仮想オーディオソフトを使うことで、ゲーム音だけを配信に乗せ、通話音は聞こえないようにすることができます。これにより、視聴者はゲームに集中でき、プライベートな会話を守ることができます。
たとえば「VB-Audio Cable」や「VoiceMeeter」を使えば、音声の出力先を細かく振り分けられます。設定を工夫すれば、Discordの通話は自分のイヤホンだけに出力し、配信にはゲーム音だけを流すといった細かい調整が可能です。配信テストを行いながらバランスを整えることで、より高品質な配信が実現できます。
配信環境を整えることで、視聴者にも通話相手にも快適な音環境を提供できます。
結果として、配信の印象が良くなるだけでなく、通話相手にも面倒をかけないので、両方にメリットがあります。
ゲーミングデバイスの使い方で変わる音環境
ゲーミングヘッドセットには、指向性マイクやミュートボタンが付いていることが多く、音漏れ対策に便利です。指向性マイクは自分の声を重点的に拾い、周囲の雑音を抑えてくれるため、通話と配信のどちらでも効果を発揮します。
また、USB接続のものは音の安定性も高く、ゲームや通話に向いています。ワイヤレスモデルを選ぶ場合も、遅延の少ない低レイテンシータイプを選ぶと、リアルタイム性が求められるゲーム配信で安心です。
さらに、外付けのオーディオインターフェースやミキサーを導入すれば、音質や音量バランスをより詳細にコントロールできます。自分の使用環境に合った機材を選ぶことで、トラブルを未然に防げます。
通話と動画を両立させるための実用テクニック

バックグラウンド再生・PIP機能の活用
YouTube Premiumや一部動画アプリでは、PIP(ピクチャー・イン・ピクチャー)機能やバックグラウンド再生が使えます。
これらの機能を活用すれば、通話中も動画を閉じずに小さなウィンドウで表示し続けたり、画面を消した状態で音声だけを再生したりすることが可能です。
通話中に別ウィンドウで小さく動画を表示できるので、操作がしやすくなり、画面を切り替える手間も減ります。たとえば、相手と会話しながら料理動画を見たり、学習用の動画を参考にしたりと、マルチタスクがしやすくなるのが魅力です。
イヤホンやBluetoothヘッドセットを併用すれば、動画の音声は自分だけが聞けるようになり、通話相手に音を聞かせずに安心して視聴できます。さらに、音量を控えめに設定しておけば、イヤホンから外に漏れる心配も少なくなります。
PIP機能を使う際には、アプリごとに対応状況が異なるため、事前に利用している動画アプリがPIPに対応しているかを確認しておきましょう。バックグラウンド再生についても、YouTubeの場合はPremium会員限定の機能となるため、必要に応じて加入を検討するのもひとつの方法です。
こうした工夫を取り入れることで、通話と動画視聴をスムーズに両立でき、相手にも迷惑をかけず快適に楽しめます。
スマホとPCで役割分担するマルチデバイス術
スマホでは通話、PCでは動画視聴といったように、2台のデバイスを使い分けることで音の混在を防げます。これにより、通話中に相手に動画の音が入り込む心配が少なくなり、安心して会話を楽しむことができます。
特に作業中やリモート会議中に便利なテクニックで、同時に複数のことをこなしたい人には大きな助けとなります。
例えば、PCでプレゼン資料や動画を確認しながら、スマホで同僚や友人と通話するといった使い方が可能です。こうすることで一台のデバイスに負担をかけず、動作の遅延やアプリの強制終了といったトラブルも回避できます。
さらに、端末ごとに役割を分けることでバッテリー消費も分散でき、長時間の作業や会議でも安定した環境を保ちやすくなります。
周辺機器を併用すれば利便性はさらに高まり、例えばPCでは大画面で快適に動画を見つつ、スマホではイヤホンマイクを通してクリアな通話を実現できます。
機器に余裕があれば積極的に取り入れてみましょう。家庭内で余っている端末を活用するだけでも、日常の通話と動画視聴の快適さがぐっと向上します。
静かな空間づくりや防音グッズの活用もおすすめ
マイクが周囲の音を拾わないよう、静かな部屋や防音カーテン、防音マットを使うのも効果的です。これらを導入することで、外部の生活音や環境音を軽減でき、相手に届く声がよりクリアになります。
また、卓上の吸音材やマイクカバーを使えば、よりクリアな音声通話が実現します。
吸音材はデスク周りに置くだけでも効果があり、マイクカバーは風切り音や息の音を和らげる効果が期待できます。こうした小さな工夫を積み重ねることで、全体の音質は大きく改善されます。
環境づくりも音漏れ防止の大切なポイントです。
自宅でのテレワークや長時間のオンライン通話でも、安心して快適に会話できる空間を整えることが重要です。
子どもや高齢者でもできる簡単な対処法

ワンタップで音を切れるシンプル操作のすすめ
イヤホンの物理ボタンや、スマホの「メディア音量ミュート」機能を使えば、すぐに音を切ることができます。
多くの機種ではイヤホンのボタンを1回押すだけで再生や一時停止、長押しでミュートなどが可能になっており、手元で簡単に操作できるのが魅力です。こうしたシンプル操作を覚えておくことで、慌てることなく通話中に不要な音を抑えることができます。
タップ1回で操作できる設定を家族と一緒に覚えておくと安心です。
特に子どもや高齢者は複雑な操作が苦手なことも多いため、ワンタッチで音を切れる方法を共有しておけば、緊急時や突然音が出てしまったときでもすぐに対応できるようになります。端末ごとにショートカットを設定しておくとさらに便利です。
誰でもわかるやさしい設定方法
iPhoneやAndroidの「おやすみモード」や「簡単モード」などを活用すると、操作がわかりやすくなります。
おやすみモードをオンにすれば通知音やアラームが抑えられ、通話に集中しやすくなりますし、簡単モードを設定しておくと文字やアイコンが大きく表示されるため、スマホに不慣れな方でも直感的に操作できます。
家族の端末にも事前に設定しておくことで、音漏れの心配が減ります。特に高齢者のスマホにはわかりやすい画面配置を用意しておくと安心です。
さらに、ショートカットやホーム画面に「音量ミュート」のボタンを追加しておくと、迷わず操作できます。
家族に教えるときの伝え方のポイント
「このボタンを押すと音が止まるよ」「このアプリを使うと通話中に安心だよ」と、具体的に説明すると伝わりやすいです。
口頭だけでなく、操作手順を紙に書いて冷蔵庫に貼っておいたり、イラストやスクリーンショットを見せながら説明することで、誰でも理解しやすくなります。
できればメモを残したり、イラスト付きで説明してあげるのもおすすめです。家族で一緒に練習してみると記憶にも残りやすく、実際に音漏れが発生した際にスムーズに対処できるようになります。
よくある質問(FAQ)
通話中に動画を流すのは非常識?
相手の状況や場面によりますが、音漏れや注意不足につながるため、控えるのが基本です。
どうしても必要な場合は、事前に一言伝えて配慮を忘れないようにしましょう。
Bluetoothなのに音が相手に聞こえるのはなぜ?
Bluetoothイヤホンでも、設定によってはスマホのスピーカーから音が出ていたり、マイクが本体側になっていることがあります。
接続状態や使用機器を確認してみましょう。
完全に音漏れを防ぐ方法は存在する?
100%の防止は難しいですが、複数の対策を組み合わせることで、かなりの音漏れを防ぐことが可能です。
イヤホン・アプリ・環境整備などをバランスよく活用しましょう。
まとめ|通話中でも動画を快適に楽しむには
自分に合った対策を組み合わせよう
スマホ・PC・アプリ・イヤホンなど、自分の使い方に合った方法を選ぶことで、通話と動画を快適に両立できます。例えば、自宅でのリモート会議ではPCを通話専用にしてスマホで動画を再生する方法が便利ですし、外出先ならBluetoothイヤホンとアプリ設定を併用すると安心です。状況や目的に合わせて柔軟に工夫することが大切です。
シチュエーションに応じて対策を柔軟に取り入れてみてください。短時間の雑談通話では簡易的なイヤホンで十分な場合もあれば、仕事の大事な会議ではノイズキャンセリング付きの高性能ヘッドセットが役立ちます。用途ごとに最適な方法を選べるよう、日頃から自分に合った機器や設定を確認しておきましょう。
相手への配慮と快適さの両立が大切
通話中に動画を再生するときは、常に相手のことを考えた行動を心がけましょう。相手が集中して話しているときには動画を止める、事前に「少し音を確認するね」と声をかけるなど、ちょっとした気遣いで印象は大きく変わります。自分が快適に過ごすだけでなく、相手も気持ちよく会話できる環境を作ることが、円滑なコミュニケーションにつながります。